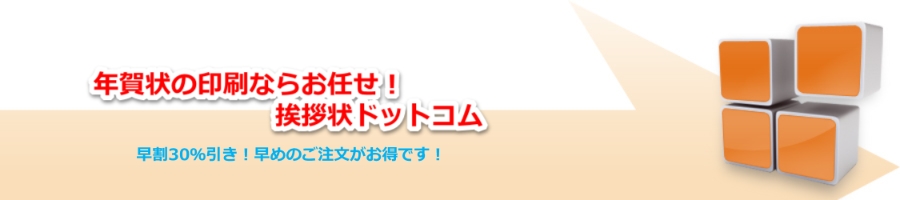カラー切手の登場
昭和25年6月から昭和28年7月までは、朝鮮戦争が行われていたことをご存知の方も多いと思います。この時、日本では特需景気が終わり、不況の世の中に移り変わっていましたが、日本全体としては成長の勢いが止まることがありませんでした。
このような状況下でも、年賀状を始めとする郵便物の取扱量も急増し、切手の需要も大幅に増えています。このため、切手の製造能力を向上させる必要に迫られた大蔵省印刷局では、昭和29年10月に最新鋭グラビア印刷機を導入します。この機器は、西ドイツのゲーベル社製のもので、輸入されたものでした。
この印刷機は4色までのグラビア多色印刷で切手を印刷できる機能を備えており、これがきっかけで日本の切手もカラー版へと形を変えていくことになりました。
そして郵政省でもこの印刷機に注目し始め、昭和30年用の年賀切手は、この機械を用いて多色刷の切手をはこうすることを企画しました。多色刷に適したものとして、あらたな案も検討。そして獅子舞や福寿草、水仙などが候補として上がりましたが、結局は前年どおりに郷土玩具が取り上げられることになりました。これは石川県金沢市の郷土玩具「加賀起上り」ですね。
その後この「加賀起上り」は正月の初売りの時の景品として使われるようになり、加賀地方では婚礼や誕生などの慶事の際の贈り物として使われるようになります。(加賀起上りを箪笥にしまっておけば、女性や子供の衣装が増えるとされていました。)
この切手の発行日には金沢市・金沢郵政局、金沢観光協会に共催によって「加賀八幡起上り意匠切手発行祝賀大会」が開催され、巨大な模型の起上りを背景に、多いに盛り上がったそうです。
スポンサードリンク