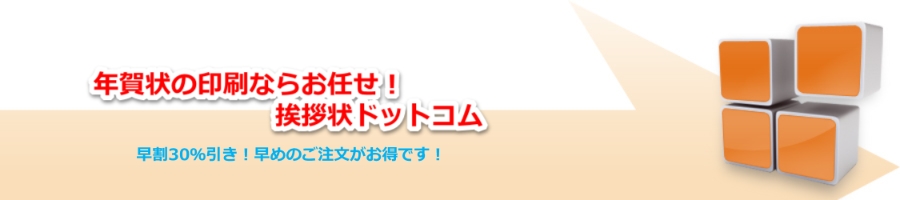年賀状の普及の歴史
新年に年賀状を交換するという歴史は、だいぶ昔から行われていました。そのきっかけとなったのが、1871年4月20日に西洋諸国を模範にした近代郵便制度が発足したことです。これを機に、賀詞を郵便で送るという風習が、自然に行われるようになりました。
その後は郵便制度の発達に伴って、郵便量の取扱量がどんどん増えていきます。それに比例して年賀状の取り扱いも増大し、1906年には年末の12月15日から29日まで、年賀状を一般の郵便物と区別して取り扱うための「年賀特別郵便規則・年賀郵便特別取扱規定」が制定されました。この時の年始に取り扱われた年賀状の数は、全国で約4億通と言われています。
そしてそれからは、関東大震災が発生した1923年と大正天皇が崩御された1926年の年末に一時中断されたものの、年を重ねるごとに年賀状の取扱量は増加。1936年(昭和11年)には、年賀状の取扱量はおよそ8億5千万通にもなったそうです。
しかし、1937年に日中戦争が始まると、非常時であるために年賀状は自粛するべきというムードが世間に広まりました。そして1938年には、年賀状の取扱量も3億2千5百万枚にまで激減。1940年には、戦時下の「虚礼廃止」を理由にして、年賀郵便の取扱は事実上廃止にされてしまいました。ただ、戦時下にあっても、年賀状を出す人がいなくなったというわけではなく、日本中が大変な状況だった1946年においても、人々は年賀状をやり取りしていたそうです。
その後1948年の年末になると、年賀郵便の特別取扱が復活しました。戦後の復興と共に、年賀状の取扱量も次第に活況を取り戻していきます。
今現在では当たり前のようになっているクジ付きのお年玉はがきですが、これは戦後の焼け野原の中で生まれたものです。当たった方への商品として、年賀切手を収めた小形シートが作られるようになりました。そして小形シートは色々と変化を重ねながら、干支の郷土玩具を取り上げたものが定番になっていきました。
スポンサードリンク